
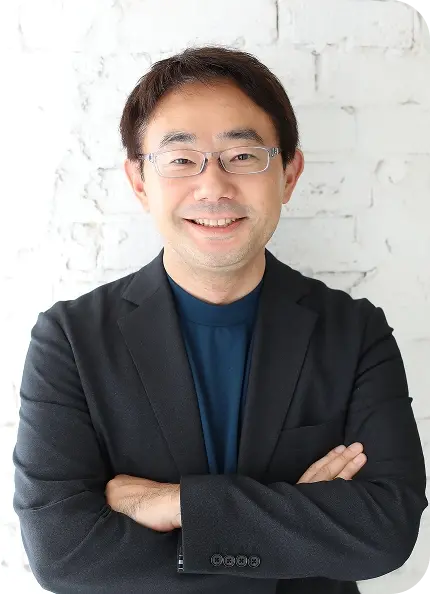
武蔵大学 社会学部 メディア社会学科 准教授
宇田川 敦史 氏
PROFILE
1977年東京都生まれ。武蔵大学社会学部メディア社会学科准教授。東京大学大学院学際情報学府博士後期課程修了。博士(学際情報学)。京都大学総合人間学部卒。
メディア研究者。専門はデジタル・メディア論、メディア・リテラシー、メディア・デザイン。
京都大学総合人間学部を卒業後、日本IBMにてWebシステムの設計・開発に携わる。その後楽天株式会社にてデジタル・マーケティング、SEO、UXデザインに従事したのち現職。デジタル・プラットフォームにおけるアルゴリズムの社会的なあり方について、メディア論・メディア史の視座から研究を行っている。また、アルゴリズムのようなメディアの「仕組み」に着目したメディア・リテラシーの育成プログラムの開発にも取り組んでいる。
主な著書に『アルゴリズム・AIを疑う: 誰がブラックボックスをつくるのか』(集英社、2025年)、『Google SEOのメディア論: 検索エンジン・アルゴリズムの変容を追う』(青弓社、2025年)、『AI時代を生き抜くデジタル・メディア論』(北樹出版、2024年)、主な論文に「検索プラットフォームと「AI」のダイナミクス」(『メディア研究』106号所収、2025年)などがある。

『アルゴリズム・AIを疑う: 誰がブラックボックスをつくるのか』(著者:宇田川敦史、発行:集英社)
AIの劇的な進歩は、社会やビジネスの在り方を大きく変えようとしている。もはや、AIが持つ可能性を理解しておかなければ、時代の趨勢を読むことはできないと言っても過言ではない。
単に「AIがブームだから」と浮足立っているだけでは、AIの本質は見えてこない。AIという言葉が市民権を得た今こそ、地に足を付けてAIに真摯に向き合っていく姿勢が求められる。
その重要性をより多くの経営者やビジネスパーソンに認識してもらうために、本ブログでは日本を代表する人工知能研究者にAIの現在地や未来像を語ってもらう企画を立ち上げた。
デジタル技術の進歩が加速する一方、人間は考える力が低下していると言われている。もっと言えば、社会で起きていることや発信されている情報に何の疑問すら抱かなくなりつつある。
そんな在り方に、問題を提起しているのが武蔵大学 社会学部の准教授・宇田川 敦史氏だ。2025年5月に発売された著書『アルゴリズム・AIを疑う 誰がブラックボックスをつくるのか』(集英社新書)では、メディア・リテラシーをアップデートする重要性を説いている。
その宇田川先生に弊社代表の山本がインタビューを試みた。
前編では、宇田川先生の研究テーマやアルゴリズムの実際などについて語ってもらった。
後編では、アルゴリズムとブラックボックス、アルゴリズムのメディア・リテラシーなどについて語ってもらった。
